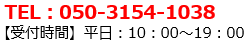この記事を読むのに必要な時間は約 12 分です。
心理的安全性とは?
心理的安全性とは、「対人リスクを恐れずに、率直に意見や質問、試行ができる状態」を指します。ハーバード・ビジネススクールのエイミー・エドモンドソン教授(1999)は、心理的安全性を「メンバーが発言しても否定や報復を受けないと感じること」によって、実験的行動(試行・提案)や学習行動(質問・相談)が促進されると定義しました。
また、MITのダニエル・キム教授が提唱した「成功循環モデル」では、関係の質 → 思考の質 → 行動の質 → 結果の質という因果関係が示されています。関係性の質が低い職場では、無難で防衛的な思考に陥りやすく、成果が出にくいとされます。そして、この「関係の質」を高める代表的な要素が心理的安全性です。心理的安全性が確保された組織では自由な発言や創造的思考が活発化し、質の高い行動へとつながります。
心理的安全性の重要性
心理的安全性は、単に「居心地の良さ」を意味するものではなく、組織やチームの生産性を左右する重要な要素です。研究や実務の蓄積からも、その効果は明らかになっています。
まず、Google社が2012年~2015年にかけて行った大規模調査プロジェクト・アリストテレスでは、180以上のチームを分析した結果、高い成果を上げるチームに共通していたのは心理的安全性の高さでした。心理的安全性があるチームでは、アイデアの質が向上し、エラー報告が増え、学習スピードが高まり、最終的に業績も改善することが報告されています。
また、心理的安全性はプレゼンティーズム(出勤していても生産性が低下している状態)にも影響します。厚生労働省やWHOの調査では、人間関係や信頼感の欠如といった心理要因が生産性損失の大きな原因であり、年間で従業員1人あたり数十万~数百万円に相当する損失につながるとされています(東京大学・川上憲人教授の試算)。
さらに、エンゲージメントの低下と離職率の高さにも直結します。ギャラップ社(2023)の調査では、心理的安全性の低い職場ではエンゲージメントが著しく低く、離職率は高い社員の2.5倍以上になると報告されています。
これらの知見から、心理的安全性は職場における発言やアイデアの活性化、学習速度の向上、離職防止、生産性の改善に直結することがわかります。つまり、心理的安全性は「人が気持ちよく働ける環境」以上に、組織の成果や持続性を高める経営上の重要要因なのです。
心理的安全性の4つの因子
石井遼介著『心理的安全性のつくり方』によると、心理的安全性は抽象的な概念に見えますが、具体的には「4つの因子」によって支えられています。それぞれの因子は職場での行動や雰囲気に直結しており、組織やチームが成果を出すための基盤となります。
1. 話しやすさ
メンバーが率直に意見や質問を出せる状態を指します。あいづちや質問を歓迎する姿勢、雑談の余地があることなど、日常のやり取りの中で「声を上げても大丈夫」と思える空気が欠かせません。これが不足すると、課題が表面化せずに先送りされ、結果的に大きなリスクを招く恐れがあります。
2. 助け合い
困ったときに支援を求めたり、逆に手を差し伸べられる関係性です。相談や協力が自然に行われることで、トラブル対応や業務改善のスピードが高まります。特に非定型業務や複雑なプロジェクトでは「一人で抱え込まない文化」が成果を左右します。
3. 挑戦
失敗を恐れずに新しいことに挑戦できる雰囲気を指します。小さな試行錯誤を繰り返し、学びを共有することで組織は環境変化に柔軟に対応できます。逆に挑戦が抑制される職場では、現状維持が続き、競争力を失うリスクが高まります。
4. 新奇歓迎
多様な視点や個性を尊重し、それを資源として活かすことです。「違いを違いとして受け止める」姿勢が、創造性や革新を生みます。多様なバックグラウンドを持つメンバーが力を発揮できるかどうかは、この因子にかかっています。
これら4つの因子は相互に作用し合い、「意見が出る → 協力が生まれる → 挑戦が試みられる → 新しい価値が創出される」という好循環を形成します。したがって、心理的安全性を高めるには、これらの因子を意識して日常のコミュニケーションや制度設計に取り入れることが重要です。
心理的安全性の作り方・高める方法
心理的安全性は自然に成立するものではなく、組織的な仕組みづくりと日常的な行動を通じて育てていく必要があります。
石井遼介著『心理的安全性のつくり方』では、その変革プロセスを「構造・環境」「関係性・カルチャー」「行動・スキル」の三層で整理しています。
1. 構造・環境を整える
まずは制度や仕組みのレベルで、意見が出やすい場を設計することが出発点です。
・会議では発言順や持ち時間を明確にし、意見が偏らないようにする
・上司と部下のパワーバランスを是正する仕組みを導入する
・プロセスや業務の制約を見直し、自由度を確保する
このような「土台づくり」によって、個人の性格や一時的な雰囲気に左右されにくい環境になっていきます。
2. 関係性・カルチャーを育てる
次に、チームの習慣や文化を意識的に変えることです。
・承認や感謝を伝える文化を定着させる
・異なる意見を歓迎し、「違い」を資源として扱う
・リーダーが心理的に柔軟な姿勢(受容・方向付け・マインドフルな見極め)を示す
この段階では、信頼や安心感を「関係性の当たり前」として築くことが求められます。
3. 行動・スキルを定着させる
最後に、具体的な行動習慣を育てます。
・リーダーが率先して質問する・失敗を共有する
・メンバー同士で相談・助言し合う
・4つの因子(話しやすさ/助け合い/挑戦/新奇歓迎)に沿った望ましい行動を増やし、不安を増幅させる行動を減らす
性格ではなく行動にフォーカスすることが、心理的安全性を継続的に高める鍵となります。
このように、心理的安全性を高める取り組みは「構造 → 関係性 → 行動」という順序で積み上げると効果的です。環境と文化が整い、行動が伴って初めて「挑戦や改善が自然に回る職場」が実現します。
心理的安全性は組織やチームの生産性向上の1つの要因すぎない
ここまでに、心理的安全性の重要性、4つの因子、さらにはその高める方法について述べてきました。心理的安全性は確かに重要ですが、それだけで組織やチームの成果が決まるわけではありません。前述のGoogle社のプロジェクト・アリストテレスの調査結果では、「個々の能力よりも、チーム全体の雰囲気や関係性が成果を左右する」というものであり、特に心理的安全性が大きな要因として浮かび上がりました。しかし、同調査では、心理的安全性だけに着目したわけではありません。調査の結果では、成果を上げるチームには共通する5つの要素があることが明らかになりました。以下はその主要な因子です。
| 因 子 | 内 容 |
| 心理的安全性 | メンバーが不安なく意見を出し、質問や懸念を率直に伝えられる雰囲気があること。 |
| 信頼性 | チームの一人ひとりが責任を持って役割を果たし、互いに信頼できていること。 |
| 構造と明確さ | チームの目的や役割、仕事の進め方や意思決定の基準が明確に定義され、全員に共有されていること。 |
| 仕事の意味 | 業務が単なる作業ではなく、個人にとって意味や価値のあるものとして認識されていること。 |
| 仕事のインパクト | 自分の仕事がチームや組織、社会にポジティブな影響を与えているという実感があること。 |
このように、心理的安全性はあくまで「複数要因の中の1つ」にすぎません。確かに土台として不可欠ですが、それだけを強化しても成果は限定的です。例えば、心理的安全性が高くても、役割や目標が不明確なチームでは迷走が起き、インパクトにつながらない可能性があります。
したがって、組織やチームの生産性を本当に高めるためには、心理的安全性を含む複数の要因をバランスよく整えることが必要です。測定や分析のプロセスを通じて「どの要因が足りていないか」を見極め、優先順位をつけて改善していくことが、持続的な成果につながります。
なお、「組織やチームの成果を分ける5つの因子」についての詳細は、組織やチームの生産性を高めるには?|鍵は“個人の能力”より“関係性の質”をご参照ください。
まとめ
・心理的安全性とは、対人リスクを恐れずに意見や挑戦ができる状態であり、現代の知識労働において組織やチームの成果を左右する土台です。背景には、非定型業務や協働型の働き方の増加があり、関係性の質が成果に直結することが学術的にも示されています。
・心理的安全性が高い職場では、発言やアイデアが活発になり、エラーや改善提案が共有され、学習速度が高まります。結果として、生産性向上や離職防止につながることが、Google社の「プロジェクト・アリストテレス」をはじめ多くの研究で確認されています。
・さらに、その鍵となるのが「話しやすさ」「助け合い」「挑戦」「新奇歓迎」という4つの因子であり、これらが相互に作用することで職場に好循環が生まれます。心理的安全性を高めるためには、会議の設計や役割分担といった構造の整備、信頼や承認を育むカルチャーづくり、そしてリーダーやメンバーの日常的な行動習慣の定着が欠かせません。
・一方で、心理的安全性は万能薬ではありません。成果を左右する重要な要因であることは確かですが、それだけで組織の生産性が決まるわけではありません。Google社の「プロジェクト・アリストテレス」が示すように、信頼性、役割や目標の明確さ、仕事の意味、成果の実感といった他の要素と組み合わせてこそ効果を発揮します。したがって、心理的安全性を単独で高めるのではなく、組織全体の心理的要因を測定・分析し、優先順位をつけて改善することが重要です。
当社では、「組織やチームの成果を分ける5つの因子」に対する分析サービス(名称:組織生産性 心理要因分析)をご提供しています。単なる分析のみならず、改善施策のヒントを併せてご提示しています。
また、調査項目数(質問項目数)は、厳選した20項目程度ですので、回答者への負荷・手間も少なく調査できます。
・組織生産性 心理要因分析(心理的安全性調査)の詳細にご関心のある方は、こちら≫よりご覧ください。
・より詳しいサービス説明資料は、問い合わせフォーム≫よりご依頼ください。
・組織診断サービス総合案内ページは、こちら≫よりご覧ください。
また、今回の記事について、もっと詳しく知りたいという方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。
050-3154-1038
受付時間 平日10:00 – 19:00