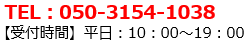この記事を読むのに必要な時間は約 16 分です。
人事評価の目的
人事評価は、昇給・昇格などの処遇に直結する制度であると同時に、社員の納得や信頼を得ることでモチベーションや組織力の向上にも大きな影響を与える重要な仕組みです。
人事評価は、一般的には以下のような目的で構築されます。
①会社組織の方針を「評価基準」という形で表し、会社組織が求めている具体的な能力・行動・成果を従業員に理解させ、従業員を会社組織が目指す方向に向かわせること
②会社組織の方向性と合致した従業員の努力や成果に対しては、公正に評価・処遇すること
③人事評価で明らかになった各従業員の強みや課題に対し、上司などの指導・助言を通じて、人材育成すること
本記事では、人事評価制度の基本原則から、納得性・公平性・透明性を高めるための具体施策、さらには制度そのものの見直しポイントまでを網羅的に解説します。
人事評価の原則
人事評価制度における重要な要素には、一般に「透明性」「公平性」「納得性」があります。
「透明性」:評価基準や評価方法等を被評価者に対してオープンにする事。
「公平性」:特定の被評価者を有利または不利に扱うことなく、評価が公平・公正に行われる事。
「納得性」:評価結果や処遇に対する従業員の納得を確保する事。
信頼性の高い人事評価を継続的に運用する上で最も重要なことは、評価に対する「納得性」を高めることであり、「納得性」を高めるためにも、人事評価制度に「透明性」「公平性」を確保する事が必要となります。しかし、制度上で「透明性」「公平性」を確保出来たからといって、従業員の「納得性」を得られるとは必ずしも言い切れません。
これらも踏まえると、人事評価に不満を抱く要因は、
①透明性の問題 ②公平性の問題 ③納得性の問題 ④評価制度そのものの問題
が考えられ、どこに問題があるのかを特定し、改善し、信頼性の高い人事評価制度としていく事が求められます。
以下では、この①~④の問題への対策ポイントについて述べていきます。
「透明性」「公平性」「納得性」の問題への対策ポイント
以下は、「透明性」「公平性」「納得性」の問題への代表的な施策です。
・人事評価に係る基準の周知(問題:「透明性」)
・フィードバック面談の実施(問題:「透明性」「納得性」)
・評価者研修の実施(問題:「公平性」)
・被評価者研修の実施(問題:「公平性」「納得性」)
人事評価に係る基準の周知(問題:「透明性」)
人事評価基準や評価結果と給与・昇進などの処遇との関連性などが、従業員に未周知または不明確な状態、評価に対する不満や不信感を高め、モチベーションを低下させてしまう可能性があります。そのような事態を回避し、会社の人的資源管理の仕組みに納得した上で、日々の仕事に取り組んでもらうために、人事制度の内容を従業員に開示し、人事制度の透明性を確保します。
また、制度内容を開示する事で、現在の給与や昇進・昇格の適正性への不満に対し、昇給・昇進・昇格が基準に基づいた人事評価の結果である事を従業員に示します。
人事制度の主な開示事項としては、以下のようなものがあります。
<人事制度の主な開示事項>
1.等級制度
①等級フレーム
能力や役割、成果責任などのレベルや大きさによって従業員の格付けを示した等級や役職、キャリアコースの全体像
②等級毎の求める人材像(等級基準)
等級毎に求める能力・役割・職務・成果責任を明記したもの
③昇格・昇進基準
(例)昇格基準ならば、「最短滞留年数」「人事評価結果」「受講研修」「試験」「面接」など
④昇給基準
人事評価結果の昇給への反映ルール
(例)人事評価結果に基づいた昇号数に現在の等級での号俸を加えた昇給方法や、昇進・昇格などの等級アップによる昇給方法など
2.評価制度
①等級毎の人事評価基準
②年間を通じた制度の運用ルール
評価期間、評価者及び評価方法、フィードバック面談の実施などによるの評価結果の伝達方法など
3.賃金制度
①等級毎の号俸、基本給、諸手当や、賞与算定方法など
基本的には全てを開示する事が望まれますが、現状の制度の運用スキルレベル等も踏まえ、現段階で透明性を担保できる部分はどのあたりなのかを十分検討した上で、段階的に透明性を高めていきます。
フィードバック面談の実施(問題:「透明性」「納得性」)
フィードバック面談とは、評価結果のみを伝える面談ではなく、評価結果の理由を伝え、部下の不満・疑問を解消するなどして、納得性を高めるとともに、評価結果に基づいて次の改善目標や課題を明確にするなど、部下の成長を支援する事を目的とした面談です。
フィードバック面談では、
・評価結果の理由(昇給・昇進・昇格等の処遇の根拠が各種基準に基づいた評価結果である事の説明も含む)
・人事評価の目的
・評価結果に対する疑問点の解消
・良かった点、改善してもらいたい点、気になった点の伝達
・部下の仕事の重要性
・部下からの要望
・評価結果に基づいたて次の改善目標や課題の設定
などについて話し合い、納得性の向上や成長支援をしていきます。
また、話し合いを通じて、上司と部下の相互信頼を深めていく事も重要です。
評価者研修の実施(問題:「公平性」)
人事評価制度を公正に機能させるためには、評価者が、会社が定めた評価項目や基準を正確に理解し、公平で客観性に評価する能力が必要となります。
評価者研修を通じて、評価者スキルの向上・均質化を図ります。
評価者研修では、
①必要な心構えの把握
②評価項目や基準の理解
③評価技能の習得
④評価者間の判断基準レベルの統一
などについて学びます。
③④は、主にグループワークを通じて学び、グループワークでは、数名ずつでグループを組み、その場にいない特定の一人について、各人が評価し、各人の評価結果やその理由などをグループ内で協議の上、グループとしての評価結果を決定します。
この過程で、評価基準への理解を深めるとともに、自身の何らかの心理的偏向(※1)に気付き、実際の評価に向けて改善に努めます。
なお、研修は1回だけでなく定期的に研修を実施することで判断基準のレベルの更なる統一が図ります。また、評価後に検討会や振り返りなど、評価者同士が集まって評価について互いの悩みや問題点の解決について話し合いの機会を設ける事も有効です。
(※1)心理的偏向
従業員が「評価が公平ではない」と感じる原因の1つで、評価者の意図的または無意識な心理や感情。
心理的偏向には、主に以下のようなものがあります。
①中心化傾向・分散化傾向:極端な評価を嫌い評価を中心に集めたり、故意に両極端に評価
②寛大化傾向・厳格化傾向:部下からよく思われたい等の心理から評価を甘くしたり、逆に厳しく評価
③ハロー効果:一部の特徴的な印象が全体的な印象になる
④論理的誤差:ある評価要素と関連性があると考えた評価要素に類似の評価をする
⑤期末誤差:全体の評価期間を見て評価するのではなく、直近の行動や印象で評価する
⑥遠近効果:時間的に近接している場合に類似の評価をする
⑦恒常効果:評価者の価値観などで、特定の項目を重視・軽視する
⑧対比誤差:評価者と被評価者の性格が対照的な場合に、過大・過小に評価する
被評価者研修の実施(問題:「公平性」「納得性」)
評価者のスキルを向上させ、公平な人事評価をすることは重要ですが、被評価者も学ぶべきことがあり、被評価者が持つべき考え方・意識を学ぶために被評価者研修を実施します。被評価者が持つべき考え方を学ぶことで、人事評価に受け身なることなく、主体的に自己成長に活かすための意識付けをします。
<被評価者研修での習得内容例>
・経営理念、会社の将来の方向性の再確認
・会社がどんな人材を求めているか
・人事評価を行う目的
・評価基準の理解
・評価結果と自身との関連
・自己評価と他者評価のギャップの理由
・評価結果の自己成長への繋げ方 など
「評価制度そのもの」の問題への対策ポイント
会社の経営戦略を人材マネジメントの側面から具体化した人事制度のうち、評価や処遇の適正性に影響するものは、等級制度、評価制度、賃金制度と言えます。
以下は、この3制度を中心とした主な再確認事項です。
<主な再確認事項>
1.等級制度に自社の経営目標を達成するために必要な人材像が規程されているか
等級制度は、従業員の格付けを示した等級毎に能力や役割、成果責任などの会社が求める人材像を明文化したもので、人事制度の根幹と言える重要な制度です。等級制度を構築する事で、従業員がキャリアアップを図る際の尺度、評価基準、昇進・昇格基準、必要な教育内容が明確になります。
したがって、人事制度の根幹をなす等級制度に自社の経営目標を達成するために必要な人材像が規程されているかを再確認します。
2.等級毎の人事評価基準は適切か
一般的な評価項目の構成要素の「業績」「情意」「能力」面の等級毎の評価基準や、高い業績を上げる人に共通の態度、価値観、知識、スキル、思考、行動などの特性を明文化したコンピテンシー評価項目が適切かどうかを再確認します。
<一般的な評価項目の構成要素>
・業績面:一定期間内に従業員が発揮した仕事の量と仕事の質や課題の達成度
・情意面:仕事に取り組む姿勢、態度や意欲、行動など
・能力面:知識、技能、コミュニケーション力、理解力、企画力などの職務遂行に必要な能力
3.昇格・昇進基準は適切か
昇格基準ならば、「最短滞留年数」「人事評価結果」「受講研修」「試験」「面接」など
4.昇給基準は適切か
人事評価結果に基づいた昇号数に現在の等級での号俸を加えた昇給方法や、昇進・昇格などの等級アップによる昇給方法など
5.評価制度の運用ルールは適切か
・評価期間
・評価者及び評価方法
・評価結果の伝達方法(フィードバック面談の実施など)
6.限りある賃金原資をどんな人材に対して配分すれば会社は成長するか
人件費は企業にとって最も大きなコストのひとつであり、限られた賃金原資をいかに効果的に配分するかは、人事制度設計において極めて重要な視点です。成長戦略と整合した賃金配分を実現するには、次のような視点が必要となります。
①会社の持続的成長に貢献する人材とは誰かを明確にすること
たとえば、新規事業を牽引できるイノベーティブな人材、収益の柱を担う営業・技術のハイパフォーマー、マネジメント層の中核となるリーダーなど、経営上の重点課題と直結する人材を特定することが出発点となります。
②戦略的配分のルールを定めること
成果主義・能力主義のバランスを踏まえたうえで、評価結果に応じた昇給幅・賞与比率を設定し、「成果の高い人材により厚く報いる」ことと「一定の貢献をした人材への公正な処遇」の両立を図る必要があります。
③人材育成と連動した配分戦略をとること
一時的な成果だけでなく、将来的な組織貢献を期待できる人材(例:高いポテンシャルを持つ若手・次世代リーダー候補など)への投資的な配分も検討すべきです。
④賃金配分の透明性と納得性を確保すること
賃金配分の考え方やルールを明示し、社員が理解・納得できる状態をつくることで、処遇に対する不満や不信感を抑え、モチベーション向上や人材の定着にもつながります。
人事評価制度の定着と運用効果を高めるには「組織風土」も重要
ここまでに、人事評価(制度)の諸問題に対する対策ポイントについて述べてきましたが、実際には、制度そのものだけでなく「職場の信頼関係」や「心理的安全性」といった職場環境・職場風土にも左右されます。
組織行動論(ウィリアム・A・カーン)や人的資源管理、組織心理学(アラン・M・サックス)の研究結果によると、エンゲージメントが高い職場では、上司や同僚との信頼関係や対話が活発であり、これが制度の受容度や納得性に影響することを示しています。また、ウィリアム・A・カーンは、心理的に安全で意味づけがあると感じられる職場環境こそが、従業員の“自己を持ち込む意欲”を高め、制度に対する主体的な関与を生み出すと述べています。
つまり、評価制度の整備とともに、その制度を活かす「職場環境整備」「組織風土の醸成」が欠かせません。
例えば、以下のようなものが挙げられます。
①上司と部下の間に「相談できる」関係性があること
従業員が懸念や疑問を率直に伝えられる環境があることで、評価の意図や意味を理解しやすくなり、制度に対する不信感の低減につながります。
②ミスや意見表明に対して否定や処罰ではなく、傾聴と学びがある文化
発言や失敗に対する罰への恐れがないことが、制度に関する率直なフィードバックや改善提案を促し、制度の運用を健全にします。
③チーム内で日常的に感謝や賞賛を伝え合う習慣
ポジティブな職場感情が信頼や協力の文化を育み、制度の「公正さ」への納得を助けます。
④発言と行動が一致したリーダーシップ
評価を司る上司が一貫性ある態度を取ることで、制度そのものの信頼性が高まり、従業員の受容度が向上します。
こうした信頼・尊重・協働の文化が根づいた職場こそが、制度の透明性・公平性・納得性すべてを土台から支え、評価制度の定着と効果的な運用につながります。
今回は、人事評価の原則である「透明性」「公平性」「納得性」とその対策ポイント、さらには、人事評価制度の定着と運用効果を高めるにはそれらを受容する「組織風土」も重要であることを述べました。
なお、当社では、組織の信頼関係・一体感・心理的安全性といった“制度を支える土壌”を可視化し、評価制度の効果を最大化するためのエンゲージメント総合診断をご提供しています(※評価制度そのものの従業員の認識の可視化も含みます)。詳細にご関心のある方は、以下のリンクをご覧ください。
エンゲージメント総合診断についてはこちら
より詳しいサービス説明資料は、こちらよりお問い合わせください。
また、今回の記事について、もっと詳しく知りたいという方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。
050-3154-1038
受付時間 平日10:00 – 19:00