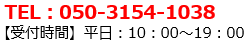この記事を読むのに必要な時間は約 12 分です。
「優秀な個人」だけでは成果は出ない ― 成功する組織・チームの本質とは?
多くの企業が「優秀な人材の確保」や「ハイパフォーマーの育成」を目指して採用・人材開発に注力しています。しかし、それだけで本当に組織全体の成果は高まるのでしょうか?
Google社が実施した大規模調査「プロジェクト・アリストテレス」は、チームの生産性を高めるために必要なものが「個人の能力」ではなく、「チームとしての関係性(集団的知性)」であることを明らかにしました。
この調査は、「従業員は単独で働くよりも、チームで働いた方が大きな成果を出せるのか?」という問いに対して科学的な答えを出そうとしたものです。そして最終的に、「チームの成功は、メンバーのスキルよりも、チーム内の“人間関係の質”に左右される」という結論に至りました。
組織やチームの生産性はなぜ集団的知性で決まるのか?
個々がいかに優秀であっても、チーム全体が協働し、同じ方向を向いて動けなければ、組織としての成果にはつながりません。むしろ、優秀な人材が集まっているがゆえに、かえって衝突が起きたり、バラバラに動いてしまったりするケースもあります。
たとえば、以下のようなチームを想像してみてください。
・一人ひとりは高スキルだが、会議では一部の人しか発言せず、議論が広がらない
・チームのゴールや優先順位に対する共通認識が薄く、判断がバラつく
・上司への信頼が薄く、報連相に迷いやためらいが生じている
・成果に対する意味づけが乏しく、「やらされ感」が蔓延している
こうした状態では、どれほど優秀なメンバーが揃っていても、チームとしての力は発揮されません。一方で、能力に多少の差があったとしても、安心して対話でき、互いに支え合い、共通の目的に向かって進めるチームは、結果的に高いパフォーマンスを発揮します。
これが、Google社の「プロジェクト・アリストテレス」が示した「集団的知性」が持つ力であり、このような部署やチームで築かれる信頼や関係性が、組織の成果を左右します。
組織やチームの成果を分ける5つの因子
「プロジェクト・アリストテレス」では、成果を上げるチームには共通する5つの要素があることが明らかになりました。以下はその主要な因子です。
| 因 子 | 内 容 |
| 心理的安全性 | メンバーが不安なく意見を出し、質問や懸念を率直に伝えられる雰囲気があるかどうか。 |
| 信頼性 | チームの一人ひとりが責任を持って役割を果たし、互いに信頼できているかどうか。 |
| 構造と明確さ | チームの目的や役割、仕事の進め方や意思決定の基準が明確に定義され、全員に共有されているかどうか。 |
| 仕事の意味 | 業務が単なる作業ではなく、個人にとって意味や価値のあるものとして認識されているかどうか。 |
| 仕事のインパクト | 自分の仕事がチームや組織、社会にポジティブな影響を与えているという実感があるかどうか。 |
この中でも、特に注目されているのが「心理的安全性」です。上司や同僚の前で失敗を恐れずに発言できたり、「分からない」「助けてほしい」と素直に言える環境は、チームの学習行動や問題解決能力を飛躍的に高めます。
実際、Googleの調査でも「チームの成功を最も予測する要因は心理的安全性である」と結論づけられています。しかし、心理的安全性があっても、目標が曖昧で信頼関係が乏しい状態では、意見は出てもまとまりに欠け、成果につながりません。つまり、「心理的安全性」はあくまで成果を生み出すための前提条件であり、他の4つの因子と連動してこそ、組織全体の生産性を支える基盤となります。
これらの要素(因子)は、組織の生産性を高める上で見過ごせない心理的要因であり、単なる業務遂行能力やスキルレベルとは異なる観点から、「人と組織の関係性」の質を表す重要な指標です。
組織の生産性に影響する心理的要因の欠如によるリスクと損失
前章で述べたとおり、組織の成果を支える心理的要因は、見えにくいながらも極めて重要です。これらが欠けている状態が続けば、組織は次第に活力を失い、深刻な経営リスクに直面することになります。以下に代表的な例を挙げます。
■ プレゼンティーズム(出勤しても力を発揮できない状態)の増加
一見、出社率は高く勤務態度も問題がないように見えても、職場やチーム内の心理的要因が欠如している場合、従業員は本来の力を発揮できません。たとえば、「発言しても否定される」「業務の優先順位が不明」「自分の役割が曖昧」「仕事の価値を感じられない」「誰に貢献しているのかが見えない」といった状態では、エネルギーの浪費や判断の迷いが生じ、集中力や創造性が大きく損なわれます。
これは「見えない損失」と呼ばれ、企業にとって気づきにくく、かつ長期的な悪影響をもたらします。
また、東京大学・川上憲人教授による調査によれば、プレゼンティーズムによる生産性の損失は、従業員一人あたり年間数十万円から数百万円にのぼることもあるとされます。これは欠勤などよりもはるかに大きな経済的損失であり、放置すれば全社的な生産性の低下を招きかねません。
■ エンゲージメントの低下と離職リスクの増加
Gallup社が2023年に日本国内で実施した調査では、心理的安全性の低い職場において、従業員のエンゲージメントが著しく低下する傾向が示されています。エンゲージメントが低い従業員は、日々の業務に意義を感じられず、受け身の姿勢となりやすいため、成果創出にも貢献しにくくなります。
加えて、同調査によれば、エンゲージメントの低い従業員の離職率は、高エンゲージメント層の2.5倍以上にもなるとのことです。つまり、組織の文化や雰囲気が心理的に不安定であればあるほど、優秀な人材の流出につながるリスクが高まります。
このような損失は、単なる「人が辞める」「成果が出ない」といった目に見える問題だけでは済みません。次第に組織内の連携が崩れ、助け合いが減り、チームとしての結束力が弱まり、さらには顧客対応や社会的信頼にも悪影響を及ぼす恐れがあります。心理的要因の欠如は、組織の基盤を静かに侵食する“沈黙の経営リスク”であることを、経営層は強く認識しておく必要があります。
組織の生産性を高める具体的なアプローチ(方向性)
繰り返しになりますが、組織やチームの生産性を本質的に高めるには、単に「能力の高い人を集める」「成果を評価する」といった対症的な対策だけでは不十分です。必要なのは、人と人との関係性の質や、心理的な構造そのものに働きかける組織設計です。
以下に、5つの心理的因子の底上げが期待できるアプローチの方向性を示します。
■ 信頼と相互理解を育む「対話の場」の設計
チーム内の信頼関係を築くためには、日々の対話の質が極めて重要です。たとえば、定期的な1on1ミーティングやチーム内のリフレクション(振り返り)を設けることで、メンバー同士が互いの考えや価値観を知ることができます。これにより、「遠慮せずに話せる」「違いを認め合える」土壌が生まれ、自然と協働の質が高まります。
■ 目標と役割の明確化、および定期的な確認プロセス
役割があいまいなままでは、責任感や達成意識は育ちません。組織レベル、チームレベル、個人レベルで目標を明確化し、それが適切に共有されているかを定期的にチェックすることが重要です。たとえば、週次または月次で目標達成度を確認し、進捗を見える化することで、迷いが減り、目標への集中度が高まります。
■ 双方向コミュニケーションと支援型マネジメント
上司からの一方的な指示ではなく、部下からの提案や悩み相談が自然と出てくる関係性をつくることが、生産性の根本改善につながります。形式的な会議だけでなく、1on1では仕事以外の価値観やキャリアについても話題にすることで、「上司=支援者」という印象が強まり、信頼関係が育まれます。
■ “意味づけ”の共有と貢献実感を醸成する仕組み
日々の業務に追われていると、「この仕事が何の役に立っているのか」を見失いがちです。そのため、仕事の意味や社会的な価値を共有する機会を意識的に設ける必要があります。たとえば、プロジェクト終了時に成果とインパクトを振り返る会を実施したり、顧客からの感謝の声をチームで共有したりすることで、「やってよかった」という実感が醸成されます。
このように、組織やチームの生産性は、目に見えるスキルや成果だけでなく、「心理的な構造(関係性の質や信頼感、共通理解など)」に大きく左右されます。だからこそ、日々の業務の中に「対話・共有・確認」といったプロセスを組み込み、チーム内の心理的な土台を丁寧に整えることが重要です。
こうした関係性の質が高まることで、自然と連携がスムーズになり、組織全体の生産性や創造性が持続的に向上していきます。
まとめ
・個人の能力に頼るだけでは、チーム全体の生産性向上は望めません。Google社の「プロジェクト・アリストテレス」が示したように、成果を上げる鍵は、メンバー間の信頼や関係性の質にあります。
・心理的安全性・信頼性・構造の明確さ・仕事の意味・仕事のインパクトという5要素が、チームの健全な関係性と成果の基盤を形成し、これらは相互に補完し合い、組織の生産性を支えています。
・組織やチームで生産性を高めるには、信頼の対話、目標のすり合わせ、双方向コミュニケーション、貢献実感の共有など、これらを意識した日常的な働きかけが、心理的な基盤を整え、組織全体の生産性向上につながります。
なお、当社では、上記「組織やチームの成果を分ける5つの因子」に対する分析サービス(名称:組織生産性 心理要因分析)をご提供しています。単なる分析のみならず、改善施策のヒントを併せてご提示しています。
また、調査項目数(質問項目数)は、厳選した20項目程度ですので、回答者への負荷・手間も少なく調査できます。
・組織生産性 心理要因分析(心理的安全性調査)の詳細にご関心のある方は、こちら≫よりご覧ください。
・より詳しいサービス説明資料は、問い合わせフォーム≫よりご依頼ください。
・組織診断サービス総合案内ページは、こちら≫よりご覧ください。
また、今回の記事について、もっと詳しく知りたいという方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。
050-3154-1038
受付時間 平日10:00 – 19:00